

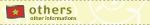
|
 |
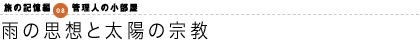
温暖湿潤な日本に暮らして、モロッコのような砂漠の国に足を踏み入れると、太陽の重さにつぶされそうになる。
夏場に外を歩けば、照りつける太陽の光に体がしぼんでいくような不思議な感覚に頭がくらくらしてくるし、冬の少し弱った光りさえ、まるで紫外線に突き刺されているかのように真直ぐにこっちに向かってくる。
日本では太陽を「お日さま」といったりして親しみを覚えることもあるわけだが、アフリカに降り注ぐ陽の光はその感覚とはまるで違うのだ。
ひたすらぎらぎらと天頂から照りつける太陽には、優しさのかけらも感じない。
そんな灼熱の大陸の片隅で、太陽が生気ををすいとり、大地を乾かす悪者のように思えてくるのとは逆に、月はまるで子守唄のように優しく、その白い光で大地をなでていく。
乾燥地帯にあるイスラムの国々の多くが、その国旗に月やら星やらをあしらうこととした理由は、夜空に月の輝く夜に、自然と体の中にしみ込んでいく。
そんな世界で生き物の生死は、水のあるなしと完全に直結している。
砂漠では、果てた命はそのまま静かに砂の上に横たわる。
チリチリに焼かれた大地の上で水分だけがひたすら天へとのぼってゆき、死体はやがて、吹き付ける風の前に、砂へと姿を変えていくことになる。
倒れるということは、命のともしびがひたすら虚空へとすいあげられる終わりを意味し、そこでうまれる感覚といえば、全ては巨大な意志のもとにあり、運命はただ一人神の手の中に、という絶望にも似たあきらめに等しい。
その非情さを前に、小さな命の一つに過ぎない自分ができることといえば、その大いなる運命を支配する神の前にひれ伏し、すがることくらいになるのだろう。
一方、豊かな水に恵まれたアジアに暮らす我々は、死、というものがそのように絶対的な力の下に支配されたものではなく、それが一つのきっかけであり、何か別なもののはじまりであるかのように、知らず知らずに感じてはいないだろうか。
道ばたで枯れ果てた草や花も、大河を流れ来る死体も、やがては「腐敗」という現象を通して、土を豊かに生まれかわらせ、新たな生命に力をあたえて行くことを知っているし、朽ち果てて倒れた木からさえ新たな命が生まれることを、我々は教わらなくても知っている。
アジアの森の湿度の中で、死はかならずしも終わりを意味しない。
生命の力に満ちあふれた自然の姿にこそ神の理を感じ取り、ごくごく身近にあるその「存在」は、自分達から離れた遠くにあるものでは決してないと感じはしなかったろうか。
圧倒的な支配力と、その全てをにぎる存在に帰依するという一神教の思想は、だから我々の文化には生まれなかったのではないだろうか…。
イスラムやキリスト教をいくら学んでも、体のどこかでどうしても神というものの唯一性を理解できないでいるのはそのせいなのではないだろうか…。
砂漠の熱気の中で乾いた風に吹かれる時、ふとそんなふうに思う事がある。
|  |